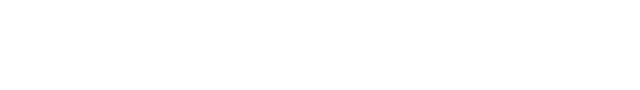内科について
当院で行っている治療
風邪,頭痛,腹痛,嘔吐,気管支喘息,花粉症,各種感染症(インフルエンザA,B,コロナウイルス感染症)骨粗しょう症などの一般内科の診断・治療.
糖尿病,高血圧,高脂血症,脳卒中,メタボなどの生活習慣病の治療.認知症の外来治療.
認知症かなと心配された御本人やご家族の方で,かかりつけ医がいらっしゃらない場合は,「認知症初期集中支援事業」という国の事業に該当します.自宅の傍の「地域包括支援センター(おとしより相談センター)」にまず相談されて下さい.板橋区は,地域包括支援センターと認知症サポート医が一対一対応しており,連携が最も進んでいます.また多比良はサポート医として成増地域包括支援センターと連携しており,認知症初期集中支援チームの一員として,多職種の方々と一緒に定期的に会議も開いており,認知症の初期の方を早く見つけて,介護や社会資源の利用や,必要なら医療に結びつけたいと考えています.早期発見と早期介入はとても大切です.かかりつけ医のいない場合は,地域包括支援センターの職員と一緒に自宅に訪問するアウトリーチ事業も積極的に行っています.
訪問看護ステーションと連携し,入院が必要な時は専門病院へ紹介し, その後のフォローアップもきめ細かく行っております.
認知症について
◆概念
認知症は,脳の病気や障害など様々な原因により,認知機能が低下し日常生活全般に支障が出てくる状態をいいます.
◆認知症を呈する主要な疾患
代表的な疾患は50%はアルツハイマー病,15%に脳血管性認知症,15%がレビー小体型認知症,その他に前頭側頭型認知症などがあります.
可逆性(治ることが可能な)認知症には,甲状腺機能低下症,慢性硬膜下血腫,正常圧水頭症,ビタミン欠乏症があります.
◆認知症の原因が解明されてきました
症状
1)中心となる症状(:中核症状)は記憶障害,判断力低下,見当識障害(日付,場所が分からなくなる),実行機能障害(料理の手順が分からなくなる)があります.
2)周辺症状として,①抑うつ(今までの笑顔がなくなり新聞テレビが面白くない,眠れないなど),②興奮(介護者に暴言暴力が見られることもあります),③徘徊(道に迷って警察のお世話になることもあります,ご家族は大変です),④睡眠障害(レビー小体型認知症では夜中に大声を出すことがあります),⑤妄想(物盗られ妄想は身近な人を犯人扱いする等介護者は大変です)などがあります.介護者が大変苦労するのは主にこの周辺症状です.
◆認知症発症前後の経過が解明されました
代表的な疾患のアルツハイマー病が仮に85歳で発症したとすると,少し前の約80歳頃軽度認知機能障害(Mild Cognitive Impairment: MCI)の状態となり,遡ること10年位前からアルツハイマー病の原因物質が体内に少しずつ蓄積していきます.アミロイドβやタウという物質です.
現在実験室段階で上記物質が採血でわかる様になってきました.またこの物質の蓄積を良くする薬も開発され最近使用可能となりました.
◆診断
最初は治療で良くなる認知症かどうかを診断します.物忘れチェック,採血,頭部CT,場合によっては頭部MRI,さらに鑑別が難しい場合は,健康長寿医療センターの精神科,脳神経内科や和光病院と連携していますので,紹介して精査が必要となる場合もあります.
◆治療(中核症状に対して)
主な治療薬には1.アリセプト(AChE阻害アセチルコリンエステラーゼ阻害薬)や,2.リバスタッチ(AChE阻害/BuChE阻害ブチルコリンエステラーゼ阻害薬),3.メマリー(グルタミン酸受容体拮抗薬)などが中核症状に対して有効です.
- アリセプト,全病期,一日5-10mg,3mgを1-2週間,5mg維持,max 10mg
- リバスタッチ,軽度-中等度,4.5-18mg貼付,4週毎に4.5mgずつup18mg維持
- メマリー,中等度-高度,一日20mg 5mgから漸増
◆認知症の経過と治療薬効果
認知症は治療なしでは時間経過と共に病状は進行します.治療薬を使用すると進行を遅らせたり,一時的に改善が認められます.根治は困難です.しかし薬を途中で止めたら,治療しなかった進行状態に進んでしまいます.根治薬は今研究段階です.
◆治療(周辺症状に対して)
介護者が大変なのは主にこの周辺症状です.
①抑うつ:高齢者にはエスシタロプラムmax 10mg分1,夕食後,また食欲低下と不眠があるときはミルタザピン7.5mgから分1就寝前
②興奮:その他幻覚,妄想,攻撃時に,第一にメマリーは穏やかにする作用も併せ持つので良いです.第二にセロトニン受容体・ドパミン受容体遮断薬のリスペリドン0.5mgから漸増20mgまでで糖尿病合併している場合も使用可能,その他クエチアピン25mgはレビー小体型認知症にも使用出来ます.また漢方薬の抑肝散も良いです,第三にテグレトール(カルバマゼピン)やバルプロ酸(デパケン)の順番に検討します.
③徘徊:元気に散歩することは本来認知症に対しては,筋肉血流と一緒に脳血流も増加するので,お薦めですが,道に迷って警察のお世話になることが多くなると介護者はとても大変です.位置情報アプリも参考にはなりますが,一人歩きは心配となります.その場合は,社会資源を利用して,一緒に散歩をしてくれるサービスを利用するのもひとつの解決策になります.まず介護保険申請して重症度ランクに応じて支援金額が変わりますので,ケアマネージャーと相談するのが一番です.
④睡眠障害:i)オレキシン受容体拮抗薬のレンボレキサント(デエビゴ)2.5mg-10mg就寝前や,スボレキサント(ベルソムラ)10-15mg就寝前は,夜中のフラツキも少なく比較的安全です.ベンゾジアゼピン系(ゾピクロン,エスゾピクロン,ゾルピデム)は夜中のフラツキ転倒の危険があり推奨出来ません.ii)メラトニン受容体作動薬ラメルテオン(ロゼレム)8mg就寝前は副作用も少なくお薦めです.レビー小体型認知症での睡眠時行動異常にはクロナゼパム(リボトリール)の使用は検討可です.
⑤妄想:幻覚,妄想,攻撃性にメマリー,リスペリドン,抑肝散を使用することがあります.レビー小体型認知症には抑肝散は幻視,易怒性,焦燥に効果をあげることがあります.
その他パーキンソン症状といって手の震え,筋肉固縮から来る最初の一歩が出にくい等の症状に対してはドパ剤が第一選択となります.上記の種々な症状でかなり複雑な場合は連携医療機関(健康長寿医療センターなど)のアドバイスを聞きながら連携して治療薬を選択していきます.
コロナウイルス感染症について
◆概念
新型コロナウイルス感染症は,2019年から世界で大流行し,ウイルス株が変異すると再び流行する可能性があります.
◆コロナウイルスの感染経路
インフルエンザと異なり,飛沫,接触だけではなく,空気中に暫く漂います.その為,窓を開けての換気が必要です.令和5年5月から5類となり,危険度が緩和されましたが,満員電車でマスクなし等が原因の感染は今も続いています.
◆コロナウイルス感染症内服治療薬が増えていますが高価です
コロナ治療薬はセットでゾコーバが15,000と高く,パキロビットとラゲブリオは30,000円以上です.指先で計測する酸素が低くなく,基礎疾患のない方は上記の薬なしで軽快することが多いです.